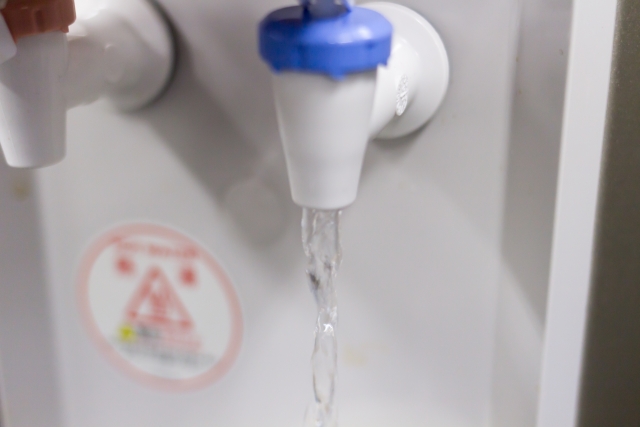TOP > 硬度とpHの目安を徹底解説!飲料水として理想的な数値と選び方のポイント
硬度とpHの目安を徹底解説!飲料水として理想的な数値と選び方のポイント
本ページはプロモーションが含まれています

水の硬度とpHの目安を知って、もっと安心で美味しい水を選びましょう
毎日飲む水について、「硬度」や「pH」という言葉を聞いたことはありますか。
水のラベルに記載されている数値を何気なく見ているけれど、実際にどんな意味があるのか、どのくらいの値が良いのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
実は、硬度とpHは水の性質を示す大切な指標で、それぞれに適切な目安があるんですよ。
この記事では、硬度とpHの基本的な知識から、飲料水として理想的な数値の目安、そして両者の関係性まで、わかりやすく解説していきます。
水選びに迷っている方、健康に良い水を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
pHとは何か?酸性・中性・アルカリ性の違い
pHの基本的な定義
pHとは、水溶液が酸性なのか、中性なのか、アルカリ性なのかを示す指標です。
0から14までの数値で表され、pH7が中性となります。
pH7未満は酸性で、数値が小さくなるほど酸性が強くなりますよ。
逆にpH7を超えるとアルカリ性で、数値が大きくなるほどアルカリ性が強くなります。
酸性・中性・アルカリ性の特徴
酸性の代表的なものには、レモン汁(pH2~3程度)や酢(pH3程度)があり、酸っぱい味が特徴です。
中性のものは、純水(pH7)が代表的で、酸味も苦味もありません。
アルカリ性のものには、石鹸水(pH9~10程度)や重曹水などがあり、ぬるぬるした感触や苦味があります。
私たちが普段飲んでいる水も、このpH値によって味わいや性質が異なってくるんですよ。
水道水とミネラルウォーターのpH目安
水道水のpH基準値は5.8~8.6
日本の水道水のpH値は、水道法によって5.8以上8.6以下と定められています。
この基準は厚生労働省が安全性と水道設備の保護の観点から設定したもので、弱酸性から弱アルカリ性までの範囲をカバーしていますよ。
実際の水道水は、多くの地域でpH6.5~7.5程度の中性付近で管理されています。
東京都水道局のデータによると、東京の水道水は概ねpH7前後の中性です。
飲料水として最適なpH値は7~8
水道法の基準値であるpH5.8~8.6の範囲内であれば安全ですが、飲料水として最も適しているのはpH7~8の範囲とされています。
東京都水道局も、飲料水として最適なpH値はpH7~8(中性から弱アルカリ性)だと発表しているんですよ。
なぜこの範囲が理想的なのかというと、人間の体液のpH値が約7.4であることが理由です。
体液に近いpH値の水は、体内に無理なく吸収されやすいと考えられています。
ミネラルウォーターのpH値は幅広い
市販されているミネラルウォーターのpH値は、採水地の地質や含まれるミネラル成分によって大きく異なります。
日本の天然水の多くは、pH7~8程度の中性から弱アルカリ性です。
一方、ヨーロッパ産の硬水は、pH7.5~8.5程度のアルカリ性傾向があるものが多く見られます。
pH8程度の弱アルカリ性の天然水は、まろやかで飲みやすく、日本人の味覚に合いやすいと言われていますよ。
硬度とは何か?カルシウムとマグネシウムの含有量
硬度の定義と計算方法
硬度とは、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を示す指標です。
これらのミネラル量を炭酸カルシウム(CaCO3)に換算して、mg/Lという単位で数値化します。
具体的な計算式は、「硬度=(カルシウム量mg/L×2.5)+(マグネシウム量mg/L×4)」となります。
カルシウムとマグネシウムが多く含まれるほど、硬度の数値は高くなるんですよ。
硬度が高いとどうなるのか
硬度が高い水は「硬水」と呼ばれ、ミネラルが豊富に含まれています。
硬水は口当たりが重く、しっかりとした飲みごたえを感じられます。
一方で、マグネシウムが多いため、人によっては苦味や渋みを感じることがあります。
また、硬度が高すぎると石けんの泡立ちが悪くなったり、水道管にスケール(白い付着物)がつきやすくなったりします。
硬度が低いとどうなるのか
硬度が低い水は「軟水」と呼ばれ、口当たりが軽くまろやかです。
日本人が飲み慣れている味わいで、料理にも使いやすいのが特徴ですよ。
軟水は石けんの泡立ちが良く、肌や髪にも優しいとされています。
ただし、硬度が低すぎると、水道管に対する腐食性が高まる可能性があるため、一定の硬度は必要なんですよ。
硬度の目安と基準値|軟水・硬水の分類
WHO(世界保健機関)の硬度基準
WHO(世界保健機関)は、硬度を以下のように分類しています。
硬度0~60mg/L未満:軟水
硬度60~120mg/L未満:中程度の軟水
硬度120~180mg/L未満:硬水
硬度180mg/L以上:非常な硬水
この国際基準は、世界中の水を評価する際の目安となっていますよ。
日本における硬度の分類
日本では一般的に、もう少しシンプルな分類が使われています。
硬度0~100mg/L:軟水
硬度101~300mg/L:中硬水
硬度301mg/L以上:硬水
日本の水道水や天然水のほとんどは硬度20~80mg/L程度で、軟水に分類されます。
水道水の硬度基準は300mg/L以下
日本の水道法では、硬度の基準値を300mg/L以下と定めています。
これは、硬度が高すぎると水道設備にスケールが付着したり、石けんの泡立ちが悪くなったりするためです。
また、東京都水道局は、おいしさの観点から硬度の目標値を10~100mg/Lと設定していますよ。
東京都の水道水の硬度は平均60mg/L程度で、軟水として飲みやすい範囲に管理されています。
地域による硬度の違い
水道水の硬度は、水源の種類によって大きく異なります。
一般的に、地下水を水源とする地域では硬度が高くなる傾向があります。
これは、地下水が地層を通過する際に、土壌中のカルシウムやマグネシウムが溶け込むためです。
一方、河川水やダム水を水源とする地域では、硬度が低めの軟水になりやすいんですよ。
日本は河川の流れが速く、地中での滞留時間が短いため、欧米に比べて軟水が多くなります。
pHと硬度の関係性|ミネラル成分の影響
pHと硬度は直接的な関係はない
pHと硬度は、それぞれ異なる水の性質を示す指標です。
pHは水の酸性・アルカリ性を、硬度はカルシウムとマグネシウムの含有量を表しています。
したがって、直接的な関係性はないのですが、間接的には影響し合うことがあるんですよ。
硬水はアルカリ性になりやすい傾向
硬水には、カルシウムイオンや炭酸水素イオンが多く含まれることがあります。
これらのミネラル成分は、アルカリ性の性質を持つ場合があります。
そのため、硬水の多くはpH7~8程度の中性からアルカリ性の傾向を示しますよ。
ヨーロッパの硬水には、pH7.5~8.5程度のアルカリ性のものが多く見られます。
軟水は中性になりやすい傾向
一方、軟水はミネラル成分が少ないため、アルカリ性になりにくい傾向があります。
日本の軟水の多くは、pH7前後の中性です。
ただし、採水地の地質や環境によっては、軟水でも弱アルカリ性や弱酸性になることもあります。
水のpH値は、ミネラル成分だけでなく、溶け込んでいる二酸化炭素などの影響も受けるんですよ。
飲料水として理想的な硬度とpHの目安
健康面から見た理想的な数値
飲料水として理想的なpH値は、前述の通りpH7~8の中性から弱アルカリ性です。
人間の体液がpH7.4の弱アルカリ性であることから、この範囲の水が体内に吸収されやすいと考えられています。
硬度については、適度なミネラル補給という観点から、硬度10~100mg/L程度の軟水が理想的とされていますよ。
この範囲であれば、カルシウムとマグネシウムを適度に摂取でき、かつ胃腸への負担も少ないです。
味覚面から見た理想的な数値
おいしい水の条件として、東京都水道局は以下の目安を示しています。
硬度:10~100mg/L
pH:7.5程度
この範囲の水は、まろやかで飲みやすく、料理にも適していますよ。
硬度が低すぎると淡白な味になり、高すぎると渋みや苦味を感じやすくなります。
pHも中性に近いほうが、クセのないすっきりとした味わいになります。
赤ちゃんや子どもには軟水がおすすめ
赤ちゃんのミルク作りや、小さな子どもの飲用には、硬度の低い軟水が適しています。
硬度が高い硬水は、マグネシウムの含有量が多く、胃腸に負担をかける可能性があります。
赤ちゃんや子どもの消化器官はまだ発達途中なので、硬度60mg/L以下の軟水を選ぶと安心ですよ。
pHについても、pH7~8程度の中性から弱アルカリ性のものが理想的です。
水選びのポイント|用途に応じた硬度とpH
日常的な水分補給には軟水が最適
毎日の水分補給には、硬度が低めの軟水をおすすめします。
日本人は軟水に慣れ親しんでいるため、飲みやすく、継続しやすいですよ。
硬度20~80mg/L、pH7~8程度の日本の天然水は、毎日飲むのに最適です。
ミネラル補給には中硬水や硬水を
ダイエットや運動後のミネラル補給には、硬度が高めの中硬水や硬水が適しています。
硬水に含まれるマグネシウムには、便通を促す効果があるとされています。
ただし、飲み慣れていない方がいきなり硬水を大量に飲むと、お腹を壊すこともあるので注意が必要ですよ。
まずは硬度100~300mg/L程度の中硬水から試してみるのがよいでしょう。
料理には軟水がおすすめ
日本料理や出汁を取る場合には、硬度の低い軟水が適しています。
軟水は素材の味を引き出しやすく、お米を炊くときにもふっくらと炊き上がりますよ。
一方、硬水は肉の臭みを取ったり、パスタを茹でるときにコシを出したりするのに向いています。
用途に応じて、硬度の異なる水を使い分けるのも楽しいですね。
pHや硬度が基準外の水は避けるべき?
水道水の基準は安全性を保証するもの
水道法で定められたpH5.8~8.6、硬度300mg/L以下という基準は、安全性を確保するための最低基準です。
この範囲を外れた水を飲むと、必ずしも健康被害があるわけではありませんが、推奨はされません。
特にpHが5.8未満の酸性度が高い水や、pH8.6を超える強いアルカリ性の水は、継続的に飲用すると胃腸への負担が懸念されます。
市販のミネラルウォーターは品質管理されている
市販されているミネラルウォーターは、食品衛生法に基づいて品質管理されています。
たとえpHや硬度が水道水の基準と異なっていても、飲用として安全性が確認されているものなので心配いりませんよ。
ただし、自分の体質や体調に合わせて選ぶことが大切です。
飲み始めて体調に変化があった場合は、水を変えてみるのもよいでしょう。
まとめ|硬度とpHの目安を知って、自分に合った水を選びましょう
ここまで、水の硬度とpHの目安について詳しく見てきました。
pHは水の酸性・アルカリ性を示す指標で、飲料水として最適なのはpH7~8の中性から弱アルカリ性です。
硬度はカルシウムとマグネシウムの含有量を示し、おいしい水の目安は硬度10~100mg/Lとされています。
pHと硬度は直接的な関係はありませんが、硬水はアルカリ性に、軟水は中性になりやすい傾向があります。
毎日飲む水だからこそ、こうした数値の意味を理解して、自分の体質や用途に合った水を選ぶことが大切ですよ。
水道水は厳しい基準で管理されているので安心ですし、ミネラルウォーターを選ぶ際はラベルの数値を参考にしてみてくださいね。
自分に合った水を見つけて、健康的で快適な毎日を送りましょう。
おすすめ記事
-
2025.10.30
エコモード効果は本当?ウォーターサーバーの電気代を最大45%削減する方法
-
2025.10.21
ウォーターサーバーでパウダー飲料を楽しもう!コスパ最強の活用術
-
2025.08.19
飲泉の効果とは?温泉を飲む健康法の驚くべき効能と正しいやり方を徹底解説!
-
2025.11.06
中空糸膜の除去性能はどこまで?バクテリア・ウイルス・化学物質を完全ガイド
-
2025.12.15
赤ちゃんに買ってはいけないお水とは?硬水NGの理由と安全な選び方を徹底解説!