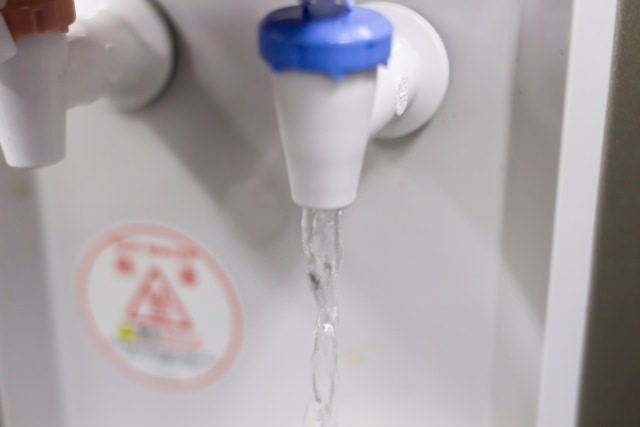TOP > 非加熱方式と加熱方式の違いを徹底解説!ウォーターサーバーの選び方完全ガイド
非加熱方式と加熱方式の違いを徹底解説!ウォーターサーバーの選び方完全ガイド
本ページはプロモーションが含まれています

ウォーターサーバーの非加熱方式と加熱方式の違いって何?
ウォーターサーバーを選ぶ際に「非加熱方式」と「加熱方式」という言葉を目にしたことはありませんか?
この2つの最大の違いは、天然水の殺菌・除菌方法にあります。
非加熱方式は、熱を一切使わずにフィルターろ過や無菌充填で除菌する方法です。
一方、加熱方式は一定の温度で加熱するか、同等の熱量で殺菌処理を行う方法なんです。
どちらも安全性に問題はありませんが、味や価格、保存性に違いが出てくるのが特徴です。
まずは基本的な違いから詳しく見ていきましょう。
非加熱方式と加熱方式の基本的な仕組み
非加熱方式の仕組み
非加熱方式では、地下からくみ上げた原水を複数段階のフィルターでろ過し、細菌やバクテリア類を物理的に除去します。
その後、無菌のクリーンルームで無菌充填を行うことで、熱を加えることなく安全な天然水を製造しているんです。
代表的なメーカーには、プレミアムウォーター、信濃湧水、リセットタイムなどがあります。
加熱方式の仕組み
加熱方式は、原水を85℃以上の高温で30分以上加熱殺菌する従来からの製造方法です。
高温処理により微生物を確実に死滅させることで、安全性を確保しています。
フレシャスの一部商品やコスモウォーターなど、多くのメーカーで採用されている一般的な処理方法ですよ。
味の違いはあるの?溶存酸素がポイント
「非加熱の方がおいしい」という話を聞いたことがあるかもしれませんね。
これには科学的な根拠があります。
非加熱方式の味の特徴
非加熱方式では、水のおいしさに影響する「溶存酸素」が減少しません。
溶存酸素は水温が上がると物理的に減ってしまうため、加熱処理をしない非加熱方式の方が、天然水本来のまろやかな口当たりと軽やかな飲み心地を保てるんです。
また、採水地由来のミネラルバランスもそのまま維持されるため、「自然のままの味」を楽しむことができますよ。
加熱方式の味の特徴
加熱処理をした天然水は、溶存酸素が多少減少するものの、ミネラル分自体は無機質なので変化しません。
「落ち着いた味」「安定した品質」を好む方には、むしろ加熱処理の天然水の方が合う場合もあります。
実際の味の好みは個人差が大きいので、常温や冷蔵庫で冷やした状態で飲み比べてみることをおすすめしますよ。
安全性の違いは?どちらも安心して飲める理由
「非加熱って安全なの?」と心配になる方もいるかもしれませんが、どちらも安全性に問題はありません。
非加熱方式の安全性
日本の食品衛生法では、加熱以外の除菌方法についても明確な管理基準が設けられています。
非加熱方式を採用するメーカーは、工場の無菌管理と充填設備の衛生管理を徹底しており、製造から密閉まで一切人の手が触れないオールロボット工程を採用している場合が多いんです。
毎日の水質検査や月1回の放射性物質検査など、品質管理も非常に厳格に行われていますよ。
加熱方式の安全性
加熱方式は従来から行われてきた確実な殺菌方法で、85℃以上での加熱により微生物を確実に死滅させます。
製造工程でのリスク管理が比較的シンプルで、品質チェックも製造途中で行えるため、高いレベルでの品質管理が可能です。
価格やコストの違いはどれくらい?
製造方法の違いは、当然価格にも影響してきます。
非加熱方式のコスト
非加熱方式は、無菌充填設備の維持や高度なフィルター管理が必要なため、製造コストが高くなる傾向があります。
そのため、加熱方式と比べて水代が月額で数百円程度高くなることが多いですよ。
ただし、味や品質を重視する方にとっては、その価格差は十分に納得できる範囲と言えるでしょう。
加熱方式のコスト
加熱方式は製造工程がシンプルで設備の維持費用も抑えられるため、比較的リーズナブルな価格設定が可能です。
コストパフォーマンスを重視する方や、家族みんなでたくさん水を使う場合には、加熱方式の方がおすすめですね。
保存性や賞味期限の違い
日常的に使う上で気になるのが、保存性の違いです。
加熱方式の保存性
加熱処理により微生物学的に安定しているため、常温保管での賞味期限が長めに設定されることが多いです。
備蓄用途や災害時の備えとしても、加熱方式の天然水は扱いやすいと言えるでしょう。
非加熱方式の保存性
非加熱方式でも、適切な密封・無菌充填・容器設計により、日常使用には十分な保存性を確保しています。
ただし、開封後は冷蔵保管で早めに使い切ることが基本となりますよ。
赤ちゃんや妊娠中の方におすすめなのはどっち?
デリケートな時期に気になるのが、どちらが安全かということですね。
赤ちゃんのミルク作りには
赤ちゃんのミルク作りには、まず「軟水」であることが最重要です。
処理方法よりも、硬度(ミネラル含有量)の方が重要で、日本の天然水は多くが軟水なので、非加熱・加熱どちらでも基本的に問題ありません。
より安心を求めるなら、硝酸態窒素や放射性物質の検査結果が公表されているメーカーを選ぶと良いでしょう。
妊娠中の方には
妊娠中も赤ちゃんと同様、硬度の低い軟水を選ぶことが大切です。
衛生管理が徹底されている日本のウォーターサーバーなら、非加熱・加熱どちらも安心して利用できますよ。
用途別おすすめの選び方
どちらを選ぶかは、あなたの使い方や重視するポイントによって決まります。
非加熱方式がおすすめの方
– 水の味にこだわりたい方
– 自然そのままの天然水を楽しみたい方
– 冷やして飲むことが多い方
– 多少の価格差は気にしない方
加熱方式がおすすめの方
– コストパフォーマンスを重視する方
– 常温保管での安定性を求める方
– 備蓄用途も考えている方
– 家族みんなでたくさん水を使う方
よくある質問(FAQ)
Q: 非加熱方式は本当に安全なの?
A: はい、安全です。日本の食品衛生法に基づく厳格な管理基準をクリアしており、毎日の水質検査も行われています。無菌充填技術により、加熱処理と同等の安全性を確保していますよ。
Q: 加熱処理でミネラルは失われないの?
A: ミネラル分は無機質なので、加熱処理によって失われることはありません。カルシウムやマグネシウムなどの栄養成分は、加熱後もそのまま残っています。
Q: 味の違いは本当にあるの?
A: 溶存酸素の量や水の構造に違いが出るため、味の違いを感じる方は多いです。ただし、個人の好みもあるので、実際に飲み比べてみることをおすすめします。
Q: どちらの方が日持ちする?
A: 一般的に加熱方式の方が賞味期限は長めに設定されています。ただし、どちらも適切に保管すれば十分な期間安全に飲むことができますよ。
Q: 価格差はどれくらい?
A: メーカーによって異なりますが、非加熱方式の方が月額で数百円程度高くなることが多いです。味や品質を重視するか、コストを重視するかで判断しましょう。
まとめ:あなたに合った選び方を見つけよう
非加熱方式と加熱方式の違いは、処理方法による味・価格・保存性の違いにあります。
非加熱方式は天然水本来の味わいを楽しめる一方、加熱方式はコストパフォーマンスと安定性に優れています。
どちらも安全性に問題はないので、あなたの生活スタイルや重視するポイントに合わせて選んでくださいね。
迷った時は、まず無料お試しサービスを利用して、実際の味を確かめてみることをおすすめしますよ。
あなたの家族にぴったりのウォーターサーバーが見つかることを願っています!
おすすめ記事
-
2025.12.11
軟水と硬水どっちがいい?違いとメリットを徹底比較!目的別の選び方を解説
-
2025.08.22
東京の水がまずいのはなぜ?本当の原因と今すぐできる対策を完全解説!
-
2025.08.25
水道水トラブルを防ぐ!赤水・異臭・白濁の原因別対策と予防法完全ガイド
-
2025.08.23
シリカ成分とは?効果・安全性・含有食品を徹底解説!美容と健康に役立つ基礎知識
-
2025.08.19
一人暮らしにウォーターサーバーは必要?メリット・デメリットと失敗しない選び方を徹底解説!




成分をやさしく解説.jpg)