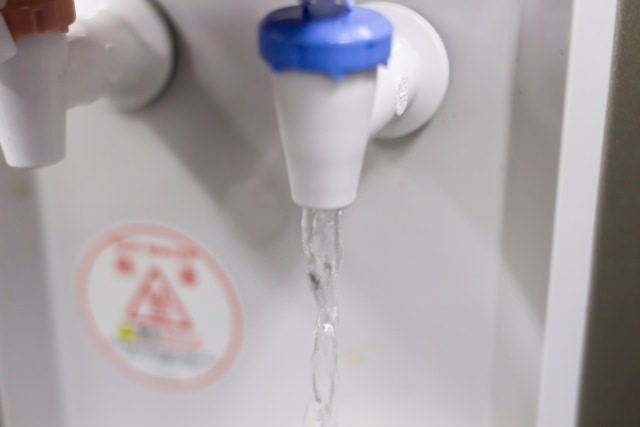TOP > リターナブルボトルの仕組みを徹底解説!回収から再利用までの流れとメリット
リターナブルボトルの仕組みを徹底解説!回収から再利用までの流れとメリット
本ページはプロモーションが含まれています

リターナブルボトル(びん)とは何か
リターナブルボトルとは、使い終わった後に回収され、洗浄・殺菌を経て何度も繰り返し使用される容器のことです。
英語の「Returnable(返却可能な)」と「Bottle(ボトル)」を組み合わせた言葉で、日本では「リターナブルびん」「リユースびん」「活きびん(生きびん)」とも呼ばれています。
使い捨てのワンウェイボトルとは異なり、リターナブルボトルは頑丈なガラスやプラスチック素材で作られており、通常20回程度の再利用が可能です。
ビールびんや一升びん、牛乳びん、ウォーターサーバー用のボトルなど、私たちの生活に身近な容器として古くから活用されてきました。
明治時代からすでに日本ではびんを回収・洗浄・再使用する文化が根付いており、持続可能な社会を目指す現代において、その価値が再評価されています。
リターナブルボトルの仕組みを徹底解説
リターナブルボトルがどのように循環しているのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。
回収から再利用までの5つのステップ
リターナブルボトルの循環は、次の5つのステップで成り立っています。
第1ステップは「販売」です。
飲料メーカーや食品メーカーが中身を詰めたリターナブルボトルを、販売店や配達業者を通じて消費者に届けます。
ビールびんの場合、商品価格に5円程度の保証金(デポジット)が上乗せされているのが一般的ですよ。
第2ステップは「使用」です。
消費者が商品を購入し、中身を消費します。
ウォーターサーバーの場合は、水を飲み切るまで各家庭で使用されることになります。
第3ステップは「回収」です。
空になったボトルは、購入した販売店や配達業者に返却されます。
ウォーターサーバー業者の場合は、新しいボトルを配達する際に同時に空のボトルを回収するシステムが採用されています。
また、自治体によっては分別収集でリターナブルびんを回収しているところもあります。
第4ステップは「洗浄・検査」です。
回収されたボトルは「びん商」や「洗びん工場」と呼ばれる専門業者に集められ、徹底的に洗浄・殺菌されます。
この工程については次の項目で詳しく説明しますね。
第5ステップは「再充填・再販」です。
洗浄・検査を通過したボトルは、飲料メーカーや食品メーカーに再販され、再び中身が詰められて市場に流通します。
このサイクルを繰り返すことで、1つのボトルが何度も使われる仕組みになっています。
洗浄・殺菌プロセスの詳細
リターナブルボトルの仕組みで最も重要なのが、洗浄・殺菌プロセスです。
回収されたボトルは、まず最新の空びん検査機で厳しくチェックされます。
キズやヒビ、変形などがないかを全数検査し、不合格となったボトルは砕かれて「カレット」と呼ばれるガラスの原料として新しいびんの材料にリサイクルされます。
検査を通過したボトルは、専用の洗びん機で内外を徹底的に洗浄します。
まず高温の洗浄液でボトル内部に付着した汚れや残留物を溶かし、次に高圧の水流で洗い流します。
多くの洗びん工場では、ライオン株式会社などと共同開発した除菌洗浄剤を使用し、衛生面に最大限の配慮をしています。
洗浄後は再度全数検査を実施し、洗浄の品質を確認します。
この二重・三重のチェック体制により、リターナブルボトルの安全性と衛生性が保たれているのです。
ウォーターサーバー業者によっては、さらに独自の品質管理基準を設けており、洗浄プロセスをホームページで公開している企業も多くありますよ。
デポジット制度の役割
リターナブルボトルの仕組みを支える重要な仕組みの一つが「デポジット制度」です。
デポジット制度とは、商品の販売時に容器代として一定金額の保証金を上乗せし、容器を返却した際にその保証金を返金する仕組みのことです。
日本ではビールびんで長年この制度が運用されており、通常1本あたり5円の保証金が設定されています。
この5円という金額は、新しいびんの製造コスト(約60円)の半分以下に設定されており、消費者にびんを返却するインセンティブを与える役割を果たしています。
デポジット制度が機能している場合、回収率は非常に高くなります。
実際、デポジット対象のビールびんの回収率は100%に近い水準を維持していますよ。
ただし、日本ではデポジット制度の実施は販売店の自主的な活動であり、地域や販売店によっては実施していない場合もあるので注意が必要です。
海外では法律でデポジット制度を義務化している国もあり、ドイツでは2003年から強制デポジット制度が導入され、ペットボトルにもデポジットが課されています。
リターナブルボトルの種類と用途
リターナブルボトルにはさまざまな種類があり、用途に応じて使い分けられています。
ビールびん・一升びんなどの飲料容器
最も一般的なリターナブルボトルが、ガラス製の飲料容器です。
ビールびんは日本で最も回収率が高いリターナブル容器の代表格で、大瓶・中瓶・小瓶の規格が統一されています。
規格が統一されているため、異なるビールメーカー間でもびんを共有でき、効率的な循環システムが構築されています。
一升びん(1.8リットル)は、日本酒や焼酎の容器として古くから使われてきました。
明治時代から使用されている歴史ある容器で、現在でも酒類販売店や飲食店で広く活用されています。
牛乳びんも昔は各家庭で見られたリターナブル容器ですが、配達システムの変化により使用量は減少しています。
しかし、宅配専門の牛乳販売店や学校給食では今でも使われており、限られた範囲での循環システムが維持されていますよ。
清涼飲料用のリターナブルびんは、約20回繰り返し使用できる設計になっています。
生協などの宅配サービスでは、調味料やジャムなどの食品容器としてリターナブルびんが採用されており、70%前後という高い回収率を実現しています。
ウォーターサーバー用リターナブルボトル
近年注目されているのが、ウォーターサーバー用のリターナブルボトルです。
ウォーターサーバー用のリターナブルボトルは、硬質プラスチック製で容量は通常12リットルまたは8リットルです。
配達業者が新しいボトルを届ける際に、使用済みのボトルを同時に回収するシステムが採用されています。
この仕組みにより、消費者は空のボトルを捨てる手間がなく、業者側も効率的に回収できるというメリットがあります。
ウォーターサーバー業界では、リターナブルボトル方式とワンウェイボトル方式の2種類が主流ですが、環境意識の高まりとともにリターナブル方式を選ぶ消費者も増えています。
回収されたウォーターサーバー用ボトルは、メーカーの工場で高温洗浄と殺菌を経て、品質検査に合格したものだけが再び使用されます。
各メーカーによって洗浄の品質管理方法は異なるため、信頼できるメーカーを選ぶことが大切ですよ。
リターナブルボトルとワンウェイボトルの違い
容器には大きく分けて「リターナブルボトル」と「ワンウェイボトル」の2種類があります。
リターナブルボトルは前述の通り、回収・洗浄して繰り返し使用される容器です。
一方、ワンウェイボトルは使い捨ての容器で、使用後は各家庭でリサイクルごみとして廃棄されます。
素材の違いも大きな特徴です。
リターナブルボトルは何度も使用できるよう、厚みがあり頑丈なガラスや硬質プラスチックで作られています。
対してワンウェイボトルは、廃棄しやすいよう薄手で柔らかいペットボトルやビニールパック素材が使われています。
価格面では、リターナブルボトルの方が一般的に安価な傾向があります。
新しい容器を毎回製造する必要がないため、その分コストを抑えられるからです。
ただし、メーカーによってはワンウェイボトルの方が安い場合もあり、一概には言えません。
環境負荷の観点では、リターナブルボトルが圧倒的に優位です。
リターナブルボトルは繰り返し使用することで、原料調達や製造にかかるエネルギーを大幅に削減できます。
ワンウェイボトルは毎回新しい容器を製造するため、製造から廃棄までのCO2排出量が多く、環境負荷が大きいのです。
利便性については、それぞれにメリットがあります。
ワンウェイボトルは使用後すぐに廃棄できるため、空のボトルを保管する必要がありません。
リターナブルボトルは回収まで保管する必要がありますが、頑丈で縦積みできるため、オフィスなど大量に使用する場所では逆に場所を取らないという利点もありますよ。
リターナブルボトルのメリット
リターナブルボトルにはさまざまなメリットがあり、持続可能な社会の実現に貢献しています。
環境負荷の大幅削減
リターナブルボトル最大のメリットは、環境負荷を大幅に削減できることです。
何度も繰り返し使用されるため、原料の採掘や容器の製造にかかるエネルギーを大幅に削減できます。
具体的な数値で見ると、その効果は驚くべきものです。
ビール500mlのリターナブルびんを20回使用した場合、リサイクルせずに使い捨てた場合と比較して、約77%も温室効果ガスの排出量を削減できます。
1日に1本の飲料容器をリターナブルびんに変更するだけで、1本あたり約100gのCO2排出を削減できるという試算もあります。
これは年間で約36.5kgのCO2削減になり、杉の木約2.6本が1年間に吸収するCO2量に相当しますよ。
回収率が高いほど、使用回数が多いほど、環境負荷は低くなります。
回収率が10%や20%ではワンウェイびんとあまり差がありませんが、回収率が向上するにつれて環境負荷は大幅に減少していきます。
廃棄物の削減効果も見逃せません。
リターナブルボトルはゴミとして廃棄されないため、埋立地の延命や廃棄物処理にかかるエネルギーの削減にも貢献します。
経済的メリット
リターナブルボトルは環境面だけでなく、経済面でもメリットがあります。
消費者にとっては、商品価格が比較的安くなる傾向があります。
新しい容器代が不要な分、価格を抑えられるからです。
ワンウェイボトルの場合、使用後の容器を捨てるためのゴミ袋も必要ですが、リターナブルボトルならその費用も節約できますよ。
企業側にとっても、長期的にはコスト削減につながります。
初期投資として洗浄設備や回収システムの構築は必要ですが、繰り返し使用できるため、容器の調達コストを抑えられます。
特に、生協や飲食店チェーンのように限られた範囲で循環するシステムでは、回収率が70%前後と高く、経済的にも成立しやすいのです。
地域経済への貢献も重要なポイントです。
リターナブルボトルの回収・洗浄を行う「びん商」や「洗びん工場」は、地域内で雇用を生み出します。
使い捨て容器が主流になると、これらの地域産業が衰退してしまう可能性がありますが、リターナブルシステムの維持は地域経済の活性化にもつながっています。
資源の有効活用
リターナブルボトルは、限りある地球資源を有効活用する仕組みです。
ガラスの原料である珪砂や石灰石、ソーダ灰などの天然資源の消費を抑えることができます。
通常、新しいガラスびんを1本製造するには約60円のコストがかかりますが、リターナブルびんを洗浄して再使用する場合、そのコストは大幅に削減されます。
20回使用できれば、1回あたりのコストは3円程度になる計算です。
プラスチック製のウォーターサーバー用ボトルも同様で、石油資源の消費を抑えられます。
使用できなくなったリターナブルボトルも、砕いてカレット(ガラスの原料)や再生プラスチック原料として、新しい容器の材料にリサイクルされます。
このように、リターナブルボトルは「リユース(再使用)」と「リサイクル(再生利用)」の両方を実現する、循環型社会の象徴的な仕組みなのです。
リターナブルボトルのデメリットと課題
多くのメリットがあるリターナブルボトルですが、いくつかのデメリットや課題も存在します。
最も多く指摘されるのが、衛生面への懸念です。
きれいに洗浄・殺菌されているとはいえ、誰が使用したか分からないボトルを使い回すことに抵抗感を持つ方もいます。
潔癖症の方や「使い回し」に精神的な抵抗がある場合は、毎回新品のワンウェイボトルの方が安心できるでしょう。
また、リターナブルボトルは硬い素材でできているため、水の使用に応じてボトルを圧縮できません。
そのため、水を使用するたびにボトル内に空気が入り込み、水が空気に触れることで劣化する可能性があります。
ただし、多くのウォーターサーバーには空気清浄システムが内蔵されており、この問題に対応していますよ。
空のボトルの保管場所も課題の一つです。
回収されるまで家に置いておく必要があるため、一人暮らしの狭い部屋では邪魔に感じることがあります。
オフィスや広い家であれば問題ありませんが、スペースに余裕がない場合は圧迫感を覚える可能性があります。
デザイン性の面では、リターナブルボトルのウォーターサーバーは選択肢が少ない傾向があります。
頑丈なボトルを剥き出しで設置するため、おしゃれなインテリアの一部として取り入れたい方には不向きかもしれません。
流通システムの維持も大きな課題です。
リターナブルボトルの仕組みは、販売店や配達業者による回収システムが機能して初めて成り立ちます。
しかし、スーパーマーケットなど大型量販店が主流になり、宅配サービスが減少すると、回収率が低下してしまいます。
実際、ビールびんの回収率は年々低下傾向にあり、2020年度のリターナブルびんの回収率は約89%と、2015年度の92%から3%下降しています。
びんの規格統一も重要な課題です。
ワインボトルのように色や形、デザインがさまざまだと、回収しても再販先が見つからず、リユースシステムが成り立ちません。
規格を統一することで、異なるメーカー間でもボトルを共有でき、効率的な循環が可能になりますが、企業のブランディング戦略との兼ね合いもあり、簡単には進まないのが現状です。
リターナブルボトルの回収率と今後の展望
リターナブルボトルの成功の鍵は、いかに高い回収率を維持できるかにかかっています。
現在、日本のリターナブルびんの回収率は約89%と、世界の先進国の中では比較的高い水準を保っています。
特にデポジット制度が機能しているビールびんは、ほぼ100%に近い回収率を達成していますよ。
生協の宅配サービスや飲食店チェーンなど、限られた範囲で循環するシステムでは70%前後の回収率を維持しています。
このように、回収システムが明確で返却しやすい環境が整っている場合、高い回収率が実現できるのです。
一方で、一般市場から回収する一升びんなどは、回収率が低下傾向にあります。
販売形態の多様化や消費者のライフスタイルの変化により、自治体の収集に出される量が増えています。
自治体によってはリターナブルびんの分別収集や抜き取りを行っているところもありますが、分別されなかったリターナブルびんはワンウェイびんと同じく砕いてリサイクルされるため、リユースの輪が途切れてしまうという問題があります。
今後の展望として、環境省では「びんリユースシステム構築に向けた実証事業」を実施しています。
びんの規格統一によるメリットの確認や、消費者の認知度向上を目的としたモデル事業が各地で行われています。
海外、特にヨーロッパではびんの利用が復活してきている風潮があります。
ドイツではペットボトルもリユースしており、匂いセンサーで分別して洗浄し、最大30回程度使用しています。
牛乳びんを100回近くリユースするなど、日本とは考え方が大きく異なりますが、環境保全を最優先にする姿勢が浸透しています。
日本でも、SDGsや持続可能な社会への関心の高まりとともに、リターナブルボトルの価値が再認識されつつあります。
行政に頼らず、生協や企業が独自に効率的な回収システムを構築する事例も増えています。
小ロットでの洗びんは割高になりますが、環境負荷削減のためにリターナブルびんを使いたいという企業も出てきており、多様なニーズに応える柔軟なシステムの構築が期待されていますよ。
まとめ:リターナブルボトルの仕組みを理解して環境に優しい選択を
リターナブルボトルの仕組みについて、詳しく見てきました。
回収・洗浄・検査・再充填・再販という5つのステップで循環するこのシステムは、明治時代から続く日本の伝統的な資源循環の知恵です。
徹底した洗浄・殺菌プロセスと二重三重の検査体制により、衛生面も確保されています。
デポジット制度がボトルの返却を促し、高い回収率を実現する仕組みも重要なポイントでしたね。
環境面では、20回使用することで約77%ものCO2削減効果があり、1日1本の変更で年間約36.5kgのCO2を削減できます。
経済面でも、長期的なコスト削減や地域経済への貢献など、多くのメリットがあります。
一方で、衛生面への心理的抵抗や空ボトルの保管場所、回収率の維持といった課題も存在します。
しかし、これらの課題に対しても、企業の技術革新や回収システムの改善により、解決策が模索されています。
私たち消費者にできることは、リターナブルボトルの商品を選ぶこと、そして使用後は必ず返却することです。
ビールびんや一升びんを購入したら販売店に返却し、ウォーターサーバーの空ボトルは配達業者に確実に渡しましょう。
一人ひとりの小さな行動が、大きな環境保全につながります。
持続可能な社会の実現のために、リターナブルボトルの仕組みを理解し、積極的に活用していきましょう。
環境に優しい選択は、未来の地球と私たちの暮らしを守ることにつながりますよ。
おすすめ記事
-
2025.08.19
飲泉の効果とは?温泉を飲む健康法の驚くべき効能と正しいやり方を徹底解説!
-
2025.11.06
引っ越し時のウォーターサーバー住所変更ガイド!水抜き方法と注意点を完全解説
-
2025.08.22
ウォーターサーバーは雑菌だらけ?効果的なクリーン対策で安全・安心な水を実現する方法
-
2025.08.19
ペット専用ミネラルウォーターとは!愛犬・愛猫に安全な水の選び方完全ガイド
-
2025.08.19
水道水とミネラルウォーターの違いを徹底比較!安全性・コスト・使い分け方を解説