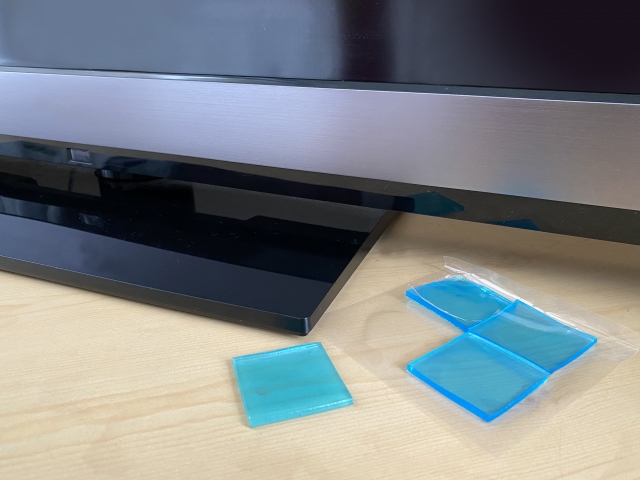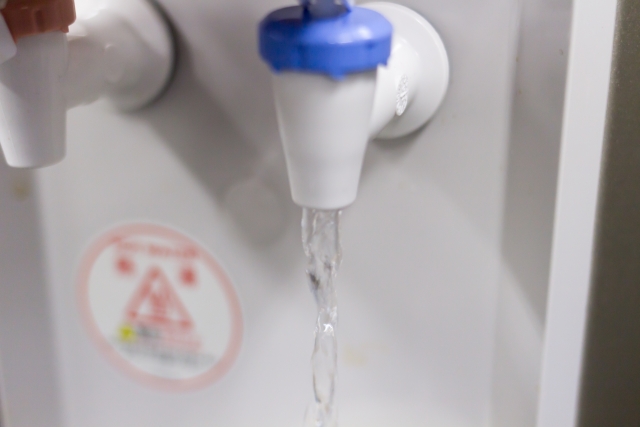TOP > 赤ちゃんの白湯はいつから?新生児には必要ない理由と正しい作り方・飲ませ方を徹底解説!
赤ちゃんの白湯はいつから?新生児には必要ない理由と正しい作り方・飲ませ方を徹底解説!
本ページはプロモーションが含まれています

赤ちゃんに白湯は必要?結論は「新生児には不要、離乳食開始後から少量ずつ」
「赤ちゃんに白湯を飲ませた方がいいの?」と悩んでいるママ・パパは多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると、**新生児(生後28日未満)に白湯を与える必要はありません**。
現在の医学的見解では、生後6ヶ月頃まで赤ちゃんは母乳やミルクだけで十分な水分と栄養を摂取できるとされています。
WHO(世界保健機関)や厚生労働省も、生後6ヶ月までは母乳・ミルク以外の水分補給は不要としているんですよ。
白湯を与える場合は、離乳食が始まる生後5~6ヶ月頃を目安に、赤ちゃんの様子を見ながら少量から始めることをおすすめします。
赤ちゃんに白湯はいつから飲ませてもいい?月齢別の目安
新生児~生後2ヶ月:基本的に不要
新生児から生後2ヶ月頃までは、母乳やミルクだけで十分です。
母乳の約88%は水分で構成されており、赤ちゃんの水分補給も同時に行っているんですね。
この時期に白湯を与えすぎると、必要な栄養素を含む母乳やミルクの摂取量が減ってしまう可能性があります。
生後3~4ヶ月:医師の指示がある場合のみ
生後3~4ヶ月頃でも、基本的には母乳・ミルクのみで大丈夫です。
ただし、便秘や発熱などで医師から白湯を勧められた場合は、指示に従って少量(5~10ml程度)から始めましょう。
生後5~6ヶ月以降:離乳食開始と共に少量から
離乳食が始まる生後5~6ヶ月頃から、白湯を試してみても良い時期です。
この頃になると、母乳やミルク以外の味に慣れる練習としても白湯は効果的なんですよ。
最初はスプーン1杯程度から始めて、慣れてきたら徐々に量を増やしていきましょう。
赤ちゃんに白湯を与える5つのメリット
水分補給のサポート
離乳食が始まると、食事からの水分摂取が重要になってきます。
白湯は純粋な水分補給として、特に暑い季節やお風呂上がりなどに役立ちますよ。
便秘改善の効果
離乳食を始めた赤ちゃんは、腸内環境の変化で便秘になることがあります。
適度な白湯の摂取は、便を柔らかくしてお通じをスムーズにする効果が期待できるんです。
母乳・ミルク以外の味慣れ
白湯は無味に近いですが、赤ちゃんにとっては新しい味覚体験です。
離乳食への移行をスムーズにする第一歩として活用できますね。
口の中の清潔維持
母乳やミルクを飲んだ後に少量の白湯を飲ませることで、口の中を洗い流す効果があります。
虫歯予防の観点からも有効とされているんですよ。
哺乳瓶以外の飲み方の練習
スプーンやストローマグでの白湯摂取は、将来の食事スタイルの練習にもなります。
赤ちゃん用白湯の正しい作り方
基本の作り方(やかん・鍋を使用)
**必要なもの:**
– 清潔なやかんまたは鍋
– 水道水またはミネラルウォーター(軟水)
– 温度計(あると安心)
**作り方の手順:**
1. やかんや鍋に水を入れ、蓋を開けた状態で強火にかけます
2. 沸騰したら火を少し弱めて、そのまま10~15分間煮沸を続けます
3. 水道水に含まれる塩素やトリハロメタンを除去するため、しっかりと時間をかけることが大切です
4. 火を止めて、人肌程度(35~37℃)まで自然に冷まします
5. 清潔な容器に移して保存します
電子レンジでの簡単な作り方
少量の白湯を作りたい場合は、電子レンジも便利です。
1. 清潔な耐熱容器に必要な分の水を入れます
2. 500Wで1~2分加熱します
3. 人肌程度まで冷ましてから使用します
**注意点:** 電子レンジは沸騰時間が短いため、気になる方は軟水のミネラルウォーターを使用することをおすすめします。
月齢別の適切な量と飲ませ方
生後4ヶ月まで:1回25ml程度
医師の指示がある場合のみ、スプーン1杯程度から始めましょう。
哺乳瓶を使用する場合は、母乳やミルクと同じ感覚で飲ませてあげると良いですね。
生後5ヶ月以降:1回50ml程度
離乳食が始まったら、食事と一緒に少量ずつ与えてみましょう。
スプーンでの飲ませ方も練習できる良い機会ですよ。
1歳以降:様子を見ながら適量を
1歳頃になると、コップやストローマグでの練習も始められます。
ただし、1日の総水分摂取量(体重1kgあたり120~160ml)を超えないよう注意が必要です。
白湯を与える最適なタイミング
お風呂上がり
入浴で失われた水分の補給に効果的です。
唇が乾燥していたり、明らかに喉が渇いている様子の時に少量与えてみましょう。
離乳食の後
食事の後の口の中を清潔に保つために有効です。
また、食事で水分が不足しがちな時の補給にもなりますね。
外出から帰った後
外出先で汗をかいたり、乾燥した環境にいた後の水分補給として活用できます。
便秘気味の時
お通じが数日出ていない時は、水分不足が原因の可能性もあります。
様子を見ながら少量ずつ与えてみてください。
白湯を与える際の重要な注意点
温度管理は絶対に守る
**適切な温度:** 35~37℃(人肌程度)
赤ちゃんの口や喉はとても敏感です。
大人が「ぬるい」と感じる程度が適温だと覚えておきましょう。
清潔な環境で作る
使用する器具はすべて清潔に洗浄・消毒してから使用してください。
赤ちゃんの免疫力はまだ十分ではないため、衛生管理が特に重要なんです。
飲ませすぎに注意
白湯を飲みすぎると、以下のリスクがあります:
– 母乳・ミルクの摂取量減少による栄養不足
– 水中毒(低ナトリウム血症)のリスク
– 下痢を引き起こす可能性
適量を守って、赤ちゃんの様子をよく観察しながら与えることが大切です。
無理に飲ませない
赤ちゃんが白湯を嫌がる場合は、無理に飲ませる必要はありません。
成長に合わせて、自然に受け入れるタイミングを待ちましょう。
白湯の保存方法と期限
保存は冷蔵庫で短期間
煮沸により塩素が除去された白湯は、保存性が低下します。
清潔な容器に入れて冷蔵庫で保存し、**できるだけその日中に使い切る**ことをおすすめします。
作り置きする場合の注意点
– 密閉できる清潔な容器を使用する
– 冷蔵庫で保存し、24時間以内に使用する
– 使用前に温度を確認し、人肌程度に温め直す
– 異臭や濁りがある場合は使用しない
使用する水の種類と選び方
水道水を使用する場合
日本の水道水は安全基準が厳しく、基本的に安心して使用できます。
ただし、しっかりと10~15分間煮沸することで、塩素やトリハロメタンを除去することが重要です。
ミネラルウォーターを使用する場合
**選び方のポイント:**
– 必ず軟水を選ぶ(硬度60mg/L以下が目安)
– 国産のものが安心
– 加熱殺菌処理されているものを選ぶ
硬水は赤ちゃんの未発達な腎臓に負担をかける可能性があるため、避けた方が良いでしょう。
ウォーターサーバーの水を使用する場合
軟水仕様のウォーターサーバーであれば、便利に白湯を作ることができます。
温水と冷水を混ぜて適温に調整できるため、時短にもなりますね。
ただし、サーバーの衛生管理は定期的に行うことが重要です。
よくある質問と回答
Q: 新生児に白湯は絶対に必要ないの?
A: はい、基本的に必要ありません。母乳やミルクで十分な水分補給ができています。医師から特別な指示がある場合を除き、生後6ヶ月頃まで待つことをおすすめします。
Q: 白湯を嫌がる場合はどうすればいい?
A: 無理に飲ませる必要はありません。赤ちゃんの成長に合わせて、時期を見て再度試してみてください。離乳食が進むにつれて、自然に受け入れるようになることが多いです。
Q: 麦茶や果汁ではダメ?
A: 離乳食開始後であれば、薄めた麦茶(ノンカフェイン)は少量なら問題ありません。ただし果汁は糖分が高いため、日常的な水分補給としてはおすすめできません。
Q: 白湯でミルクを作ってもいい?
A: ミルク作りには70℃以上のお湯が必要です。これは粉ミルクに含まれる可能性のある細菌を殺菌するためです。白湯(人肌程度に冷ました湯)とは用途が異なりますので、使い分けてください。
Q: どのくらいの期間保存できる?
A: 冷蔵庫で保存し、24時間以内に使い切ってください。煮沸により塩素が除去されているため、保存性が低下しています。
まとめ:赤ちゃんの白湯は焦らず、様子を見ながら始めましょう
赤ちゃんの白湯について、大切なポイントをまとめると以下の通りです。
**時期:** 新生児には不要、離乳食開始(生後5~6ヶ月)頃から少量ずつ
**量:** 生後5ヶ月以内は25ml程度、それ以降は50ml程度を目安に
**温度:** 35~37℃の人肌程度を厳守
**保存:** 冷蔵庫で24時間以内に使い切る
**注意点:** 無理に飲ませず、清潔な環境で作り、飲ませすぎないこと
何より大切なのは、赤ちゃんの様子をよく観察しながら、無理をせずに進めることです。
白湯を嫌がったり、母乳・ミルクの飲みが悪くなったりした場合は、一度中止して様子を見てくださいね。
育児は一人一人違うペースがあります。
周りと比較せず、あなたの赤ちゃんに合ったタイミングで白湯デビューを果たしてくださいよ。
不安なことがあれば、遠慮なく小児科医や助産師さんに相談することをおすすめします。
あなたと赤ちゃんが安心して過ごせるよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
おすすめ記事
-
2025.08.27
東京の水はまずいは嘘!現在の水質と昔まずかった理由を徹底解説
-
2025.08.28
天然水からRO水に換える5つの理由!コストと安全性で賢い選択を
-
2025.10.17
ウォーターサーバーの転倒防止対策5選!賃貸でもできる地震対策を徹底解説
-
2025.08.29
アウトドアでウォーターサーバーのお湯を賢く活用!キャンプ・BBQで大活躍の持参テクニック
-
2025.08.20
ウォーターサーバーがぬるい原因と対処法!お湯・冷水の温度トラブル完全解決ガイド